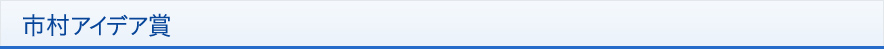受賞団体訪問
| 培われた地域の伝統を土台に、評価して伸びる児童の「発想力」 |
| 第54回(2023年度)奨励団体賞 個人賞6作品受賞 愛知県刈谷市立 日高小学校 |
 |
|
個人賞受賞の児童たちと、淵上麻由美校長(後列左)、野田憲二教頭(後列右)、理科主任の稲垣亘教諭(後列中央)
|
「ものづくり」の意識は家庭で育つ |
||||||
|
2023年度第54回市村アイデア賞は、前回を2,600件以上越える32,688件という多くの応募を全国からいただきました。 今回、奨励団体賞と朝日小学生新聞賞など6人の個人賞受賞を果たした愛知県刈谷市立日高小学校(以下、日高小)におうかがいしました。 刈谷市はトヨタ系企業が多数存在する、「ものづくり」に対する意識の高い地域です。また市村アイデア賞においても、数多くの強豪校がひしめく地域として知られています。日高小も31回の奨励団体賞受賞以降、6回の団体賞受賞を誇る強豪校のひとつです。 野田教頭によると「夏休みの理科研究は普通1年程度のものが多いのですが、本校には3年間継続して研究をする児童がいます。これは子供だけの力では難しく、家庭での協力が必要です。そういう意味でもこの地域は各家庭の教育への意識が高いのが特色です」とのこと。また淵上校長も「受賞した児童が『将来子供にアドバイスができる大人になりたい』と言うのも、自分たちが家族と一緒に考えたりアドバイスをされたりする経験が影響していると思います」と地域の特徴を語ってくれました。 日高小では昨年より、児童たちの学びを積み上げていくことを目的に、「キャリア教育」に力を入れています。理科においては、児童たちが「自分で考え、仮説を立てて、実験していく」という問題解決学習を実践しているそうです。 こうしたお話から、家庭で育まれた興味や好奇心が、学校の教育を通して具現化していく、という環境がしっかり作られていることを感じます。
|
地域や学校で積み重ねてきた力 |
||||||||||||
|
日高小において、市村アイデア賞の中心となったのは、昨年赴任された理科主任の稲垣教諭です。全校の児童に参加してほしいという強い思いから、まずは職員会議で先生方への協力のお願いから始めたそうです。先生方には授業での事前説明や過去の受賞作品の紹介などを必ずしていただき、刈谷市で統一して使用されている「創意工夫理科研究ガイド」を児童に配布。掲載している優秀作品を児童たちに紹介したり、稲垣先生が独自に作られたアイデア作りのポイントをプリントで配布したりするなど、児童の意欲を上げていくさまざまな工夫をされてきました。 「今回、団体賞を受賞できたことは大変うれしく思っていますが、受賞したのは、やはり地域の『ものづくり』の伝統や、これまでの日高小の先生方の積み重ねの成果だということを強く感じています」と稲垣教諭。実は稲垣教諭、小学校から大学まで刈谷で育ったという生粋の刈谷っ子。体験のなかで培われた稲垣教諭の「ものづくり」に対する強い思いや、コンクールに対する熱い思いは、児童たちにも影響を与えていたのは間違いないでしょう。
|
||||||||||||
「声かけ」が児童の自信となっていく |
||||||||||||
|
地域、家庭、学校とさまざまな環境で「ものづくり」や「考えて実践する」ことを育まれている日高小の児童たち。しかし、そのなかで重要なのは「声をかけて児童を評価する」ことだそうです。コンクールでは、工作の精度や緻密さも重要な要素となりますが、それが苦手な児童にも面白い発想をする子供はいます。そういう児童に自信をつけさせていくには「声をかけて評価していることを伝える積み重ねが大切」と稲垣教諭は語ります。 また市村アイデア賞について、野田教頭は「緻密な工作だけでなく、ちょっとした工夫やユニークな角度からの発想なども評価していただけることをうれしく思っています」と語ってくれました。 最後に淵上校長は「今回の受賞が、児童たちの自己肯定感や自信を高めたことを大変ありがたく思います。またこの経験は、児童たちの将来にもつながっていくと思います。キャリア教育という面でも『なぜこの学びが必要なのか』『この学びはどういう力になるのか』『この学びは将来にどうつながるのか』を児童たちが意識していくよい機会になりました」と語ってくれました。 |
||||||||||||
個人賞受賞のみなさんにお聞きしました |
||||||||||||
(取材日 2024年1月31日 愛知県刈谷市)
|