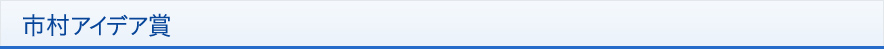受賞団体訪問
| 小規模校の利点を生かした細やかな教育で育つ「主体性」と「行動力」 |
| 第54回(2023年度)努力団体賞 市村アイデア奨励賞受賞 福山市立 精華中学校 |
 |
||
|
個人賞受賞者と妹尾進一校長(中央右)、杉原雅明教頭(右端)、理科担当の平信二教諭(左端)
|
生徒全員にある役割と活躍の場 |
||||||
|
第54回市村アイデア賞において福山市立精華中学校(以下、精華中)は、第51回からの4回目の挑戦で初の努力団体賞と市村アイデア奨励賞の受賞を達成しました。 福山市は広島県東部にあるJFEスチールを筆頭に金属、繊維、機械製造業の集積地として知られている産業都市です。精華中はその福山市の南西部の長閑な田園地帯、金江町にある全校生徒101名の小規模校です。精華中では、小規模校の利点を生かし「生徒が主役」を合い言葉に生徒の主体性と、生徒間のコミュニケーションを重視した教育を進めています。 「本校では体育大会の種目や練習計画などは、すべて3年生が考えています。また、2年生の修学旅行の行程も生徒たちが考え、旅行会社にプレゼンして実現していくなど、生徒が創り上げる過程を大切にした取り組みをしております」と妹尾校長は語ります。また理科担当の平教諭は「生徒の数が少ないですから、全員が何かの役割を果たす、全員が発言することが自然と求められます。1年から3年の生徒を一緒にした縦割りでのグループ学習や、理科以外の教科でもディスカッションや相互評価を重視していますので、その中で生徒たちの主体性は育っているのだと思います」と語ってくれました。小規模校だからこその細やかな指導の中で、主体性と考える力、表現する力を磨いている精華中の姿が伝わります。また、個人賞の受賞作にも現れているように、生徒の目線が地域の生活に向いていることも精華中の特色だと感じます。
|
4年間の積み上げと工夫が団体賞に結実 |
||
|
精華中が市村アイデア賞への取り組みを始めたのは、2020年からだそうです。ちょうどコロナ禍で授業もままならないなか、家で生徒たちが自分だけでも取り組めることはないか、と模索していた平教諭が、以前教育委員会から回ってきていた市村アイデア賞の案内を思い出し、取り組むことに決めたそうです。最初の年は夏休みの宿題として生徒に指示しただけだったそうですが、2年目は、授業内で自分のアイデアを発表し合う、3年目からは自分のアイデアをプレゼンさせて相互評価をしあう、など回を重ねるごとに生徒たちがお互いに刺激しあう工夫をしていったそうです。「中学の理科ですから、知識もしっかり身につけさせないといけません。本校では少人数だからこそ、『何度も繰り返し体験して身につける』ことを徹底しています。また『発想には必ず理由を考える』『相手の発想を受け入れ、自分の意見を伝える』ということも各教科で重視しています」と平教諭。まさにこの姿勢が、4回目の挑戦で精華中を団体賞受賞へ導いた力だと思います。 最後に妹尾校長は「身近な生活のなかに、科学に関連することはたくさんあります。生徒たちが疑問に思ったことを試行錯誤して自分の力で解決していく。そういう発想や行動力はこれからの人生の中で非常に重要だと思います。生徒たちにきっかけを与えるのが学校教育の役割のひとつかと思いますが、市村アイデア賞はそういう生徒たちに励みや自信を与える機会になっておりありがたく思っています」と語ってくれました。
|
(取材日 2024年1月25日 広島県福山市)