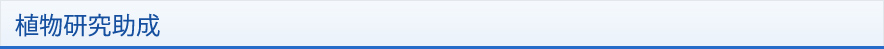
植物研究助成 20-03
伊豆半島における外来植物群落の撹乱条件に対する植生学的評価
| 代表研究者 | (財)地球環境戦略研究機関 国際生態学センター 上席研究員 村上 雄秀 |
【 背景 】 |
| 外来種は日本の生物多様性保全の上の三大危機の一つである(生物多様性国家戦略2010)。日本の外来植物は1,553種に達し在来植物約7,000種の20%を越える(環境省2002)。かつて市街地などの人工景観域のみで観察された外来植物は海岸などの自然植生にも侵入し、在来の希少種と競合しつつある。在来種の絶滅に外来種が関与した例もある(岩槻 2001)。ノハカタカラクサなどの林内生の外来種も昨年度調査で確認され、その拡大の把握と防除は急務である。 |
【 目的 】 |
| 外来植物の侵入・定着には人為的な撹乱が関与する(宮脇 1977)。しかし多くの外来植物は撹乱耐性型とされるのみでその撹乱の内容や質は明らかでない。本研究は外来植物の侵入・定着に際しての環境や撹乱の選択性を明らかにすることを目的に、様々な自然度階級の植生において外来植物の定着量と種組成、人為/自然撹乱の質的・量的な関係を解析し、外来植物の侵入を抑制する環境条件の評価を行う。伊豆半島は海洋性気候の下で海岸草原から山地のブナ林まで多彩な自然植生が残存する一方、観光地、丘陵の里地・里山、山地でのシカ食害まで植生への多様な撹乱がみられ本研究のフィールドとして適する。 |
【 方法 】 |
| 23年度は伊豆半島の丘陵に残存する神社林や代償植生域である植林地、里地・里山などに生育する在来植物/外来植物群落を対象に網羅的な植物社会学的調査を実施する。各群落について被覆指数(Deckungswert: Braun-Blanquet 1964)や出現頻度から外来植物の侵入量を数値化する。その結果を植生の環境、撹乱条件の面から評価・解析し、外来植物の定着の選択性を明らかにする。 22年度の沿海部におけるソナレセンブリなどの希少種やイガオナモミなどの外来種の群落調査に引き続き、本年度は丘陵地の植生を対象とし、里地の従来の管理およびその近年の変化に伴う外来種の侵入様式や、林内生の外来種の動向、対照としてのイズカニコウモリなどの希少種の群落調査を実施する。次年度の山地の調査とともに、内陸域における外来植物の侵入特性の解析を行う。 |
【 期待される成果 】 |
| 伊豆半島にはヤブツバキクラスからブナクラスにおよぶ多様な植生が発達し、比較的均質な地理的・気候的な環境下で外来植物や在来植物の撹乱条件への応答が把握できる。本地域の外来植物の侵入特性の研究は植物研究園を含む伊豆半島の生物多様性の保全に直接、寄与するとともに、海に囲まれた日本のモデルとして広く全国に普遍化できる。また里地・里山における人為的管理の変化や野生動物の過度の増加による外来植物の定着の実態については広く日本各地に共通の状況として適用可能であり、外来植物防除の基礎的資料となる。 |














