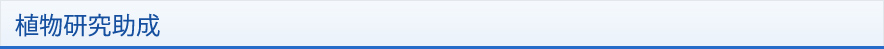
植物研究助成 20-06
高速シーケンス技術を利用した果樹栽培土壌の環境評価システムの開発
| 代表研究者 | 山梨大学 大学院医学工学総合研究部 准教授 鈴木 俊二 |
【 背景 】 |
| 植物を育てる上で、土壌の重要性は言うまでもない。土壌の性質は、構成粒子の違いによる物理的性質、イオンによる化学的性質、そして土壌生物による生物的性質により決定する。永年性作物である果樹では、土壌の性質が一度崩れると元に戻すことが難しく、回復するのに数年の年月が必要となる。物理的および化学的性質を計測する技術は確立済みであり、果樹農家もこれらの計測を定期的に行っている。対して、土壌生物は多種多様であり、これを解析することは容易ではないため、生物的性質を評価する方法は未だ開発途中である。 |
【 目的 】 |
| 本研究は、果樹栽培土壌の環境評価システムを開発するために、「高速DNAシーケンス技術」を用い、土壌中の微生物(菌類、細菌)を網羅的に同定することを目指す。土壌中には、純粋培養できない、あるいは難培養性の微生物が多い。そのため、従来の人工培地を用いた土壌微生物の同定技術では、土壌に存在する微生物の約1%しか同定できない。前年度は、定期的に採取した植物研究園梅林の土壌から、高速DNAシーケンス(パイロシーケンス法)により、約4000の菌類に相当するDNA塩基配列を得ており、難培養菌類、未同定菌類の存在を確認した。今年度もまた同土壌を定期的に採取し、土壌中に生息する菌類の属種および優先種の同定を行い、再現性および年度変化を確認する。また、山梨大学ブドウ園の土壌でも同法による同定作業を行い、梅林土壌と比較することにより、本研究が提案する環境評価システムの有効性を評価する。 |
【 方法 】 |
| 植物研究園梅林および山梨大学ブドウ園を研究フィールドとする。梅林では、前年度にあわせ、年4回(6、8、11、2月)、地下30cmの土壌を採取する。ブドウ園では8月および2月に採取を行う。土壌から直接DNAを抽出後、菌類のrDNA遺伝子をPCR法により増幅し、高速DNAシーケンスに供試する。得られたDNA塩基配列情報から属種を決定し、前年度のデータと照らし合わせ、データの再現性を検討するとともに、梅林とブドウ園とのデータ比較も行う。 |
【 期待される成果 】 |
| 果樹栽培土壌の性質は、果実品質に直結する。本研究が目指す果樹栽培土壌環境評価システムにより土壌の生物的性質が解析できれば、土壌に生息する優先種と果実品質との相関関係も解析できる。また潜在的に存在する病原微生物が同定できれば、病害予測にも適応可能である。本評価システムは、生態系の整った植物研究園梅林土壌から開発を推し進めるが、本年度はブドウ園のデータを比較対象とすることで、他果樹栽培への本評価システムの展開も図る。 |














