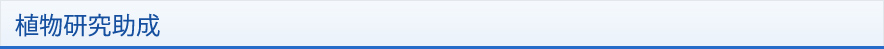
植物研究助成 20-09
植物研究園水域に堆積する植物残渣からのメタン生成に関する研究
| 代表研究者 | 大阪府立大学 大学院生命環境科学研究科 助教 遠藤 良輔 |
【 背景 】 |
| 温室効果ガスのメタンは、有機物が嫌気的な条件下で種々の微生物によって分解され、最終的にメタン生成古細菌によって分解される過程で生じる。嫌気的な環境は富栄養な湖沼・湿地帯に多くみられるが、生活排水の流入等による富栄養化のため、近年では多くの水域でメタンの発生が確認されている。植物研究園は、ワサビ田が成立するような清涼な条件に恵まれた湿地を有しているが、研究園内下流のため池土壌中においては、一部が嫌気的環境となっていることが2010年の調査で確認された。池中に落葉の堆積が見られることから、主に植物残渣の分解が嫌気的条件下で行われていることが示唆される。今後、地球温暖化および富栄養化の促進に伴うメタン生成量の増大が懸念される。 |
【 目的 】 |
| 研究園内水域における水質および植物残渣バイオマス量調査と、水域土壌を用いたメタン発酵実験及びメタン生成シミュレーションから、植物研究園水域からのメタン生成について解析を行うことを目的とする。 |
【 方法 】 |
| 植物研究園にて水質および植物残渣量のモニタリングを、大阪府立大学にてメタン発酵実験を行う。園内水域の上流及びため池に、pH・酸化還元電位(ORP)・水温計測器・植物残渣捕集網を設置し、一年にわたり連続的にモニタリングを行う。これにより、メタン発酵に適した環境が形成される季節を把握する。また、月に一度、上記の場所で採水・ガス捕集を行い、無機塩類・化学的酸素要求量・ガス組成の分析を行うことで、植物研究園内の水域環境がメタン発酵成立に及ぼす影響について把握する。大学では、植物研究園内の池中から採取した土壌を嫌気的条件下におきメタン発酵特性を調べる。投入基質には植物研究園内で採取した植物残渣を用いる。水温および基質投入量を数段階変化させて得られるメタン生成量・蛍光の変化を計測し、既に構築したメタン発酵消化モデルに代入して、植物研究園内水域におけるメタン生成ポテンシャルについてシミュレーションを行う。最後に、植物研究園内における植物残渣からのメタン生成リスクと、これらをバイオマスとして回収・利活用した場合のエネルギーポテンシャルについて解析を行う。 |
【 期待される成果 】 |
| 植物研究園においては、過去の研究により園内植物の三次元構造からバイオマス賦存量が求められている。本研究は、これに園内のメタン生成量および将来の生成リスクを付与し、植物研究園における植生および環境微生物がもたらす地球温暖化抑制への貢献度を可視化できると考えられる。さらに、植物残渣の効率的利用による温暖化緩和効果についても定量化することが期待できる。 |














