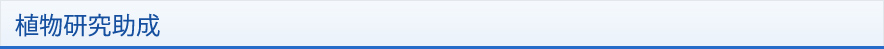
植物研究助成 20-10
シダ植物における繁殖様式に関わるゲノム領域の解析
| 代表研究者 | 東京大学 大学院理学系研究科 附属植物園 助教 角川 洋子 |
【 背景 】 |
| シダ植物は被子植物と異なり、独立生活をする両性の配偶体を形成し、単一の配偶体上で受精し胞子体を形成する自配自家受精が可能である。しかし、山野に普通にみられるシダ植物ゼンマイは、実験条件下でもほとんど自配自家受精を行なわない。これは、ホモ接合体が致死になったり生存率が低下したりする致死遺伝子や有害遺伝子が含まれていることによるものだと考えられる。一方で、ゼンマイの姉妹種であるヤシャゼンマイでは自配自家受精が頻繁に起こる。シダ植物において繁殖生態学的に重要な形質について遺伝学的に解析された例はほとんどないので、ゼンマイとヤシャゼンマイにおける繁殖様式の違いに関わるゲノム領域を明らかにしたいと考えている。 |
【 目的 】 |
| ゼンマイとヤシャゼンマイの自然雑種から作成した人工交配集団を用いて遺伝地図を作成し、マッピングした分子マーカーにおける分離比の歪みの解析を行なったところ、ゼンマイでみられる対立遺伝子をホモにもつと生存率が著しく下がったり、逆にヘテロにもつと生存率が高くなったりするゲノム領域があることが示唆された。ゼンマイは自配自家受精をほとんど行わないだけでなく、集団遺伝学的な解析から他殖性が高いことが明らかになっているので、本研究ではゼンマイの自然集団において、実際に上記のゲノム領域が他殖性に関わっているかどうかを明らかにする。 |
【 方法 】 |
| 函南原生林と植物研究園内のゼンマイを採集し、遺伝地図上にマッピングされた分子マーカーの解析を行い、各集団内のヘテロ接合度を調べる。特に、遺伝地図作成に用いた種間雑種由来の人工交配集団において、ゼンマイの対立遺伝子がホモになると生存率が著しく下がったり、ヘテロになると生存率が高くなったりする分子マーカーは、一つの連鎖群上にまとまっているので、その連鎖群について重点的に調べ、ゼンマイの自然集団でも個体の生存率と相関があるかどうかを明らかにする。また、5月上旬に園内のゼンマイから胞子を採集し、人工交配実験を行なうことにより、上記の遺伝子座におけるヘテロ接合体の生存率が有意に高いかどうかを調べる。 |
【 期待される成果 】 |
| 自殖を妨げ他殖性を促進する機構は、被子植物においては自家不和合性が 知られ、遺伝学的な解析も行なわれている。シダ植物の多くの種についても、繁殖器官の形態からは自配自家受精が可能であると考えられる場合でも、実際には他殖性が高いことが知られている。既に遺伝地図が作成されているゼンマイを材料として用いることにより、シダ植物において初めて他殖性に関わる遺伝的背景を明らかにできると期待される。 |














