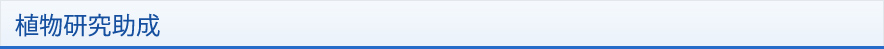
植物研究助成 20-13
伊豆半島の海岸自生植物を利用した屋上緑化の研究
| 代表研究者 | 千葉大学 大学院園芸学研究科 造園学領域 助教 永瀬 彩子 |
【 背景 】 |
| 近年、都市環境は悪化し、ヒートアイランド現象、都市洪水、生態系損失など深刻な問題を抱えている。建物の屋上を緑化する屋上緑化は、緑化面積が限られている都市部で、このような問題を解決する手法として注目されている。屋上は、耐荷重による土壌の厚さの制限、強風、乾燥、地温の変動など、植物にとって過酷な生育環境となるため、耐乾性のある外来種や園芸種が使用される傾向がある。生態系保護の観点から、屋上における自生種の利用が望ましいが、種子や苗の入手が困難であり、外国産の自生種であることも多く、自生種を利用した屋上緑化技術は確立されていない。一方、伊豆半島では独自の海岸自生植物群落が見られ、塩水飛沫、薄い表層土、晴天時の水不足等、屋上環境に非常に類似した環境に生息しているため、屋上緑化への利用の可能性は高い。海岸自生植物群落は希少となりつつあるため、保護も視野に入れた緑化素材の研究が望まれる。また、周囲の自然植生に近い植生を屋上で用いることは、地域性生態系保全の役割も果たす。 |
【 目的 】 |
| 本研究は、生物多様性を考慮した地域の植生による自生植物を利用した屋上緑化モデルを提供することを目的としている。本研究では、屋上緑化の材料として伊豆半島の海岸自生植物を用いるが、他地域でも応用できるモデルの確立を目指す。 |
【 方法 】 |
| 伊豆半島の海岸の植生調査を行い、植物及び種子、表土ソッド(植物の茎葉・根茎・土壌を含むマット状の植生断片)を採取する。温室において、採取した植物の耐乾性を調査する。また、種子の発芽特性や休眠打破の調査を行う。さらに、屋上環境で異なる人工土壌厚及び灌水頻度における表土ソッド、苗、混合種子で定着した植物の生長を解析し、屋上環境に適応できる種を選択する。さらに屋上環境の植生と現地の植生とどのように異なるのか比較を行う。なお、屋上緑化実験は、植生地からできるだけ近い場所の建物で行う。 |
【 期待される成果 】 |
| 今までの屋上緑化の植栽はアメニティを中心としたものが多かった。しかし、 本研究は、地域の特徴ある生態系を創出し、自生種の保護の役割を担うという点で、屋上緑化のみならず都市緑化に重要な貢献をすることが期待できる。また、地域の自生種を使う屋上緑化のモデルとして、他の地域での汎用性も高い。さらに、植物生理学では、海岸自生植物の耐乾性や種子の発芽生態の理解を促し、生態学の分野では、自然の植生を人工環境に移植した際、どのように生態系が変化するかという知見を提供できる。このように地域の植物を身近な屋上に植栽することは、学校における環境教育や町づくりにもつながる。 |














