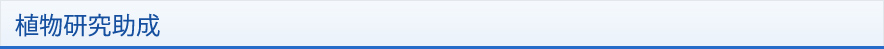
植物研究助成 34-08
接ぎ木の活着前後における水輸送および生育実態の把握
| 代表研究者 | 大阪公立大学大学院現代システム科学研究科 教授 大山 克己 |
【 背景 】 |
| 接ぎ木は、遺伝的に園芸生産に好ましい形質を有する穂木と主に病害抵抗性を有する台木とをつなぎ合わせて個体を形成する栄養繁殖法であり、農園芸分野において広く利用されている。ただし、接ぎ木直後から穂木と台木が活着するまでの間、維管束が接続していないために、接ぎ木体内での水輸送(吸水および蒸散)は抑制される。一方、穂木と台木の維管束が接続した活着後では、水輸送の抑制は緩和する。この活着前後における水輸送実態の変化に起因して、生育は変化することが予想される。しかし、接ぎ木の活着前後における水輸送および生育実態を詳細に調べた例は限られる。 |
【 目的 】 |
| 本研究では、植物工場のような環境を制御できる条件下において、接ぎ木の活着までの期間短縮や活着率の向上にかかわる知見を得るために、工学的手法を取り入れた植物の生態研究手法確立の一環として、トマト接ぎ木の活着前後における水輸送および生育実態を連続的に計測するための装置を開発する。また、環境条件が水輸送および生育実態におよぼす影響を把握する。 |
【 方法 】 |
| 供試植物には、トマト(Solanum lycopersicum L.)を用いる。接ぎ木チューブを利用して、穂木と台木とを斜め継ぎする。接ぎ木後、光合成有効光量子束密度および飽和水蒸気圧差が異なる条件下において、Van leperen and Madery(1994)の示した方法にもとづいて、蒸散および吸水速度を連続的に推定する。また、深度カメラを用いて撮影した画像から投影葉面積および草丈を連続的に推定する。さらに、接ぎ木の生育(生体重、乾物重および葉面積)および維管束の接続状況を、接ぎ木後0、2、4、6および8日目に計測する。 |
【 期待される成果 】 |
| 本研究で開発したトマト接ぎ木の活着前後の水輸送および生育実態を連続的に把握できる計測装置を用いれば、植物工場を利用した接ぎ木に好適な環境条件の探求が容易になる。工学的な視点を農園芸分野に取り入れることによって、これまで、栽培試験やこれまでの経験によって定めていた接ぎ木に好適な環境条件を、定量的な根拠をもって決定できるようになる。本申請の計測にもとづいて決定した植物工場内の環境条件により、接ぎ木の活着までの期間短縮や活着率の向上が期待される。 |















